お疲れ様で~すのトミー爺です。
最近、頑張ってつぶやいているTwitterの一部を紹介させてください。
【トミー爺の今日のつぶやき】から
作詞、作曲の勉強。解る事と使える事は違う。
音楽の大先輩の言葉。
「レコードは擦り切れるまで聞き倒せ、音楽は耳で勉強するもの」。
本や楽譜で音楽を勉強するのも良い、だけど最後は自分の耳で判断をする。
それが身につくってことだと思う。
いい言葉をいただきました。
そうです、、、、今回は「作詞、作曲の勉強。わかる事と使える事とは違う」という事について一緒に考えてみましょう。
この記事の内容は
- 作詞、作曲の勉強。解る事と使える事は違う。
- 音楽って理屈ではなく耳で覚えるもの…
- ある日、あの時、理解できなかったことが突然見えてくる
- トミー爺の経験。若い時スタジオでの会話「音が上がる」って何?
- イントロのピアノが音が上がっていて明るすぎる
- その理由、原理が分かれば使えるようになる
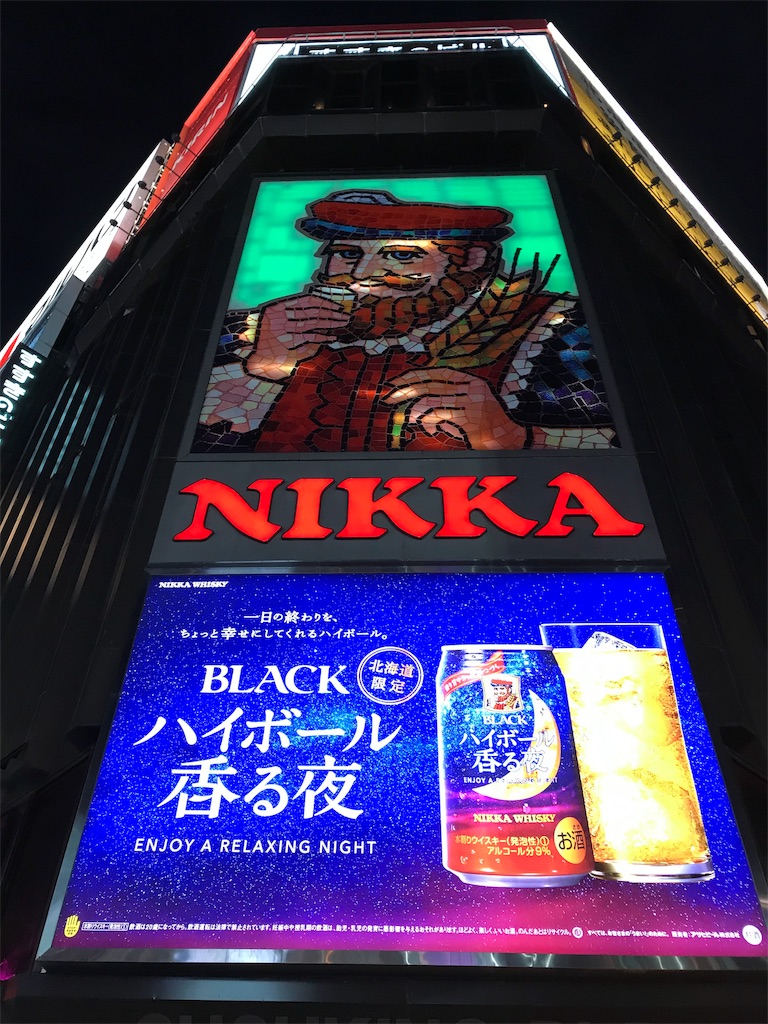
まいどまいど何でニッカの看板?
トミー爺がお酒が好きだから、、笑い。
音楽って理屈ではなく耳で覚えるもの…
ちょっと目線を変えて読書について考えてみましょう。
本を読む時にこんな経験ありませんか?
一度目読んだ時よりも、2度目、3度目読んだ時の方が深く理解が出来るって、、
- 一度目読んだ時は概要が頭に入る
- 二度目読んだ時は、一度目読んだ概要がベースにあるからより深く理解が出来る。
- 三度目読む時は、もっと深く読み進む事が出来る
これと同じで音楽って何度も何度も聞いて勉強するものだと思います。
ある日、あの時、理解できなかったことが突然見えてくる
例えば、作詞、作曲を勉強していて色んな事を言われたり、気が付いたりしますね、、でもその時はまだ身についていないはず。
その時、気が付いた事、勉強したことはあなたの記憶のハードディスクに格納されただけなんだと思います。
それにはまだ引用タグが付いていない状態。
それが何度も音楽を聞いていると、歌詞を読んでいると、昔「へぇ~そうだったんだ」という、あの時にハードディスクに格納した知識と耳から入ってくる情報が結びつく瞬間が来ます。
その時がやっと理解出来るスタートラインに立てた…という状況だと思います。
トミー爺の経験。若い時スタジオでの会話「音が上がる」って何?
若い時にスタジオ仕事をしている時、ミュージシャンやエンジニアの人たちの会話って「何となく理解できる状況でした」
例えば、
「この音って上がるからダメ!」
これを聞いた時って
「何となくわかる…」
「でも音が上がるってどんな感じなのかわからない…」
「でもこの状況は知ったかぶりしておいた方が安全、、」
なんて思っていた。
ところがそれから20年くらい経って、デモを聞いていて時に、その時の情報が初めて理解出来たんです。
音が上がるってことは、音の延びている余韻ってありますね。
その余韻の成分、、これって低音、中音、高音ってあるけど、その低音、中音の順で音が減衰してくる。
残るのは高音ですね。
低音減衰 → 中音減衰 → 高音減衰
つまり音の余韻が上がる…って事なんです。
エネルギーが無い音、、という事です。
音に芯が無い時に起きる現象で、その音がオケの中に入った時は音にエネルギーが無い音で、ミキシングでどんなに音量を上げても最終的には聞こえてこない音になる。
では逆は音が下がるって事で、先ほどの真逆な音です。
イントロのピアノが音が上がっていて明るすぎる
あるアーティストのレコーディングをしていて、すごく哀愁のある楽曲をレコーディングしていました。
そしてイントロがピアノだけ…
そのピアノの音が上がっていたんです。
イントロでしっとりさせたいのに音の余韻が上がっているので、妙に明るく聞こえてしまう。
これに気が付いたのは、実は先ほどのデモを聞いて音の上がり下がりを理解してから、さらに10年くらいたった時でした。
つまり音楽を聞き倒せっていう事は昔覚えた知識を呼び起こす機会を多くするってことなのかもしれませんね。
その理由、原理が分かれば使えるようになる
では今日の本題「解る事と使える事は違う」ってどういう事?
例えば、オーディオ雑誌等で
〇〇の音にはコンプをかけて〇〇のようにする。
という記事があったとします。
あなたは「〇〇にはコンプか?」と理解してとにかくコンプをかける。
ある作詞教則本で
作詞は〇〇のように〇〇を表現すると〇〇だ
みたいな事が書かれていて、あなたはその通りにしてしまう。
これは間違っていません。
ただ、その理由を知る事で、そのテクニックを10倍、100倍に活用できるようになります。
そのコツは
「何で?どうして?何のために?」
という気持ちを持つことで本に書かれている事を深く理解できるようになるはず、、
最初からは無理でも続ける事でそれが可能になりますよ。